生きた化石カブトガニ。
いかにも数億年生き延びたといった旧式っぽいボディーがたまらない節足動物です。
日本では瀬戸内海で見られる貴重な天然記念物。
でも、東南アジアでは屋台で食える魚介類だし、輸入物は家で飼育もできる。
あまり珍重されてる感なしなのも愛嬌といえば愛嬌ですかね。
しかし、その血液が現代医療に不可欠なもので、無視できない生物でもある。
すごいような、すごくないような……。
カブトガニはとてもスローライフで、過酷な時代を生き抜いてきたようです。
その真実を明かしてゆくとともに、似て非なるカブトエビとの関係にも触れてみましょう。
カブトガニの生態。長寿の秘密
カブトガニは4億5000万年前には誕生していました。
これはオルドビス紀に当たり、恐竜が現れる2億年も昔。
三葉虫や、3mもあるウミサソリなどがいた時代です。
その間、数度の大絶滅というカタストロフィーを生き延びてきました。
で、カブトガニも最初は「三葉虫に近い生物」と考えられてきました。
たしかに多足の三葉虫がカブトを被り、尖った尻尾を出せばカブトガニに近い気がします。
しかし、カブトガニはクモやサソリの近種。
分類では鋏角類になる。
そのくせ、甲殻類グループの短尾目のカニ、長尾目のエビ、曲尾目のヤドカリと一緒に、尾の形から「剣尾目」とされるので、ややこしくなっているんですよ。

カニの尾はフンドシのことです
カブトガニの大きさと寿命
日本から中国・東南アジアと、大西洋で4種類のカブトガニが知られます。
日本のものが一番大きく、頭から尻尾の先まで70~85cm。
メスのほうが大柄です。
交尾はメスの上にオスが重なって行いますが、たまに間違ってカメに乗っかっちゃう天然もいる。
だから天然記念物ってわけじゃないんだけど。
寿命は20~40年と推測されます。
節足動物としてはかなり長寿ですね。
ただし活動するのは主に産卵期の夏場で、それ以外はほとんど動かないらしい。
砂に沈まない平べったい体で、ダラダラとゴカイなどを漁っています。
この省エネが長い寿命の秘訣かもしれません。
カブトガニの独特な形
カブトガニをひっくり返してみると、中身スカスカです。
この無駄の多さが「生きた化石」って感じがします。
映画『エイリアン』の幼虫?を思い出す人も多いと思う。
裏から見ると「クモだな~」と納得できるでしょう。

目は1000個ほどの複眼が2つと、光を感じる目が中央に1つ。
食べ物を口に運ぶ、小さなハサミ付きの腕が2本。
その後ろに5対の肢。
腹部にえらがあって、突き出たサーベル状の尾。
馬蹄形のカブトでガードしているので、英語では「Horseshoe Crab」。
まあ、馬蹄よりはギョウザの形に近い気がするけど。
銅の混じった血液が青というのもエイリアンっぽい。
映画のデザインも絶対モチーフにしてると思う。
地球外的で、「くだらない生き物」にも見えるカブトガニですが、この血液が「世界を救う」優れものだったのです。
カブトガニは社会に貢献している!?
カブトガニの特殊な血液は、エンドトキシンという毒を凝固させます。
その感度は驚異的!
濃度が1兆分の1でも反応するのです。
エンドトキシンは微量でも高熱やショック症状をもたらす可能性がある。
医薬品に混入していると、とても危険。
そこでカブトガニの血液を素に作られた試験薬LALを用い、安全を確認したものが我々に投与されるのです。
カブトガニ様様ですね。
しかし、心配もあります。
カブトガニの血液を巡る問題
LALを作るため、カブトガニは捕獲されます。
工場で30%の血を抜かれ、海に返されるのですが、採血されたカブトガニが死んでしまうことも多い。
3割も血を抜かれたら、僕だってヘロヘロになって倒れますよ。
カブトガニ自体も産卵場所が限定され数が減っているのに、血液採取を繰り返すことでさらに減少を加速させているわけです。
カブトガニがいなくなったらLALは作れないのか?
もちろん、代用品の研究もされ、成果もあげています。
カブトガニなしでも試験できそうなのですが、新薬がなかなか実用化されない。
これにはカブトガニ工場の陰謀説も囁かれています。
なぜなら、カブトガニの血液は1リットル170万円という高額。
新薬が出回ってこの利権を失うとなれば、業界が実用化を妨害するのもわかりますよね。
現在では新薬も出回り始めていますが、カブトガニの受難はまだ終わりそうにありません。
食用からペットまで
その一方で、カブトガニは食用にされたり、ペットにされたりもする。
「どこを食うんだろう?」と思ったら、主に卵なんだそうです。
あのカブトがちょうどいい鍋になって、網焼きに都合がいい。

ホタテの殻みたいなもんですかね
殻の中にたくさん卵を抱える姿が、お金を貯めこんでいるようで、縁起物扱いされています。
僕も機会があれば「一度食ってみたい」と思ってるんだけど
「不味い」
「臭い」
と評判はよろしくない。
愛玩動物としては10cmほどのカブトガニがペットで売られています。
成長が遅いので、60cm水槽でもあればじゅうぶんでしょう。
何年も飼育して50cmにもなったら、広い容器にすればいいです。
必要なのは潜れるだけの砂くらい。
海水と餌の入手ができれば、飼育そのものは難しくないようです。
「カブトガニは淡水でも飼える」という話もありますが、これは嘘。
たしかに汽水でも生きてゆけるカブトガニですが、淡水は無理でしょう。
淡水飼育はカブトエビと混同されているのが原因のようです。
カブトガニとカブトエビは全然違う

カブトエビは関東以西の田んぼでよく見かける生物です。
僕の住む北海道にはいないんですが、東北の一部では見られるようです。
団扇型の見た目がカブトガニにそっくり。
「カブトエビが大きくなったらカブトガニになる」と信じている人もいるかもしれません。
カブトガニとカブトエビは実はまったく違う生物です。
カブトエビは淡水飼育の甲殻類
カブトエビは原始的な甲殻類の一種。
こっちも2億年生き抜いている、なかなかの強者です。
ミジンコなどの仲間で、背中の殻が広く丸くなっているのでカブトガニみたいに見えるだけ。
寿命も2ヶ月程度で、成長しても50cmのカブトガニにはなりません。
それでも大きいものは10cmに届くということで、ミジンコと馬鹿にはできません。
やはりペットにもされ、淡水飼育が基本。
田んぼの生き物ですからね。
採取してきてもいいですが、カブトエビ飼育セットみたいなのが楽でしょう。
寿命が短く、すぐ全滅してしまいますが大丈夫。
土の中に産まれた卵は、土が乾いても数年生きています。
そのまま一年保存しておき、翌年の春に水を入れればまた湧いてきます。
カブトガニではこうはいきませんからね。
しかし、カブトガニも卵を採取して孵化、成長させることは難しくなく、保護のために幼カブトガニの放流も行われています。
まとめ
日本でもカブトガニが上陸する浜は減っています。
日本産のカブトガニは絶滅寸前だそうです。
野生で見られなければ、岡山県笠岡市のカブトガニ博物館にでも行ってみましょう。
世界で唯一のカブトガニがテーマの博物館だそうです。
カブトガニの実物を見れば、あの垢抜けないスタイルに魅了されるに違いありません。
「この形で4億年生きてるんだな~」と、地球の時間軸を感じるのもいいと思いますよ。


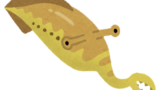


コメント
兵庫県笠岡市ではなく岡山県笠岡市です!
ありがとうございます。<(_ _)>
修正しました。